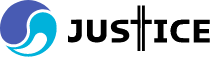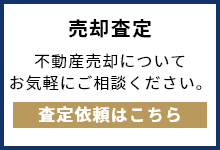「負動産」が生む静かな危機──日本各地で広がる“持て余す不動産”の現実
◆ 「負動産」とは?資産が“負担”に変わる瞬間
不動産は本来、「資産=プラスの財産」とされます。
しかしその一方で、**使い道がなく、売れず、維持費ばかりかかる“負担の財産”**となってしまった不動産を、「負動産(ふどうさん)」と呼びます。
しかしその一方で、**使い道がなく、売れず、維持費ばかりかかる“負担の財産”**となってしまった不動産を、「負動産(ふどうさん)」と呼びます。
たとえばこんな不動産が負動産の典型です。
人が住まなくなった地方の空き家
山林や原野、農地など、利用目的のない土地
賃貸や売却が難しい老朽アパート
親から相続したが、遠方で管理もできない物件
◆ 負動産が引き起こす主な問題
❶ 維持費・税金という“出費”
代表的なのが、固定資産税・都市計画税。
たとえ使っていなくても、毎年納税義務が発生します。
空き家でも更地でも、逃れられません。
たとえ使っていなくても、毎年納税義務が発生します。
空き家でも更地でも、逃れられません。
特に空き家を解体して更地にすると、住宅用地の特例(税額が1/6または1/3)がなくなり、税金が数倍に跳ね上がるケースも。
❷ 管理放棄による“地域トラブル”
長年放置された空き家は、建物の劣化が進み、以下のような問題を引き起こします。
屋根や壁の崩落リスク
ゴミの不法投棄、害虫・害獣の発生
雑草の繁茂による景観悪化
放火や不審者の侵入による防犯上の問題
結果として、近隣住民とのトラブルに発展するケースも少なくありません。
❸ 市町村の負担と財政問題
国土交通省の調査では、空き家は全国に約849万戸(2023年時点)。住宅全体の13.8%にもなります。
地方自治体では、増え続ける空き家に対応しきれず、行政代執行(強制解体)による費用負担や、治安・景観悪化による住民離れが深刻です。
❹ 相続人にとっての“迷惑な遺産”
誰も使わない土地や家屋が相続された場合、その不動産が負動産であると…
登記手続きが面倒
固定資産税が負担
売却もできない
処分に費用がかかる
という、「相続したら逆に損する」ケースに直面します。
特に2024年4月からは「相続登記の義務化」により、相続した不動産の登記を3年以内に行わないと10万円以下の過料が科される可能性もあります。
特に2024年4月からは「相続登記の義務化」により、相続した不動産の登記を3年以内に行わないと10万円以下の過料が科される可能性もあります。
◆ なぜ負動産は放置されるのか?
● 売れない(ニーズがない)
人口が減り、都市への一極集中が進む中、地方の不動産は買い手がつかない状況に陥っています。
● 処分にお金がかかる
空き家の解体費用は100万円~200万円以上が一般的。
売却してもマイナスになるなら、放置したほうが「損しない」と思う人も多いのです。
売却してもマイナスになるなら、放置したほうが「損しない」と思う人も多いのです。
● 所有者不明土地の増加
長年放置され、相続も登記もされず、「誰のものか分からない土地」が日本中に約410万ヘクタール(九州本島に匹敵)存在するとされます(国土交通省調査)。これも深刻な問題です。
◆ 解決の糸口はあるのか?
✅ 早めの専門家相談がカギ
負動産になる前に、早い段階での相談や活用法の検討が重要です。
空き家バンクの利用や、賃貸への転用、隣地所有者への売却、農地転用など、思わぬ活用策が見つかることもあります。
空き家バンクの利用や、賃貸への転用、隣地所有者への売却、農地転用など、思わぬ活用策が見つかることもあります。
✅ 補助金制度を活用しよう
多くの自治体で、空き家解体補助金やリフォーム支援金制度が用意されています。
「どうにもならない」と諦める前に、まずは地元役場や不動産会社に問い合わせを。
「どうにもならない」と諦める前に、まずは地元役場や不動産会社に問い合わせを。
✅ 国の制度改革も進行中
国も対策に本腰を入れており、
相続登記の義務化(2024年~)
所有者不明土地の利用促進
空き家対策特別措置法の改正(2023年)
などの制度が順次施行されています。
◆ まとめ:不動産は“放置”が一番危ない
負動産の問題は、あなたの家族や地域、そして社会全体にじわじわと影響を与える“静かな危機”です。
今は価値がなくても、使い道を見直す・早期に手放す・周囲と協力することで、将来のトラブルを防ぐことができます。
「うちの実家も将来そうなるかも…」
「親名義の土地、このままで大丈夫?」
そんな心配が少しでもある方は、“今”行動を起こすことが何よりも大切です。
「親名義の土地、このままで大丈夫?」
そんな心配が少しでもある方は、“今”行動を起こすことが何よりも大切です。