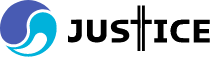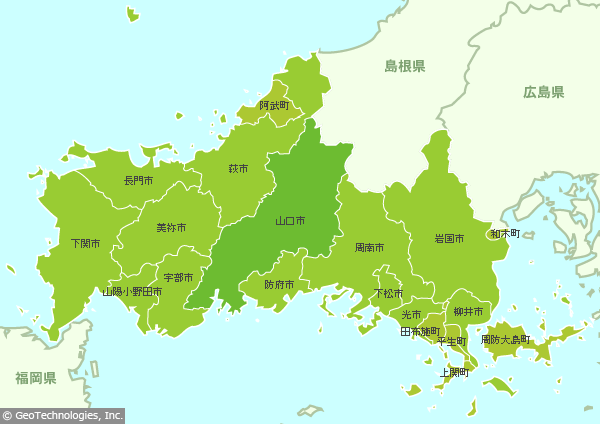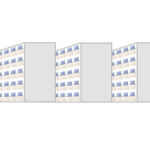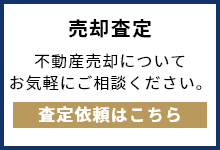山口県で「コンパクトシティ構想」は可能か?
近年、人口減少と高齢化が進む地方で「コンパクトシティ」の議論が盛んです。山口県でも“まちの機能を集約して暮らしやすさを守る”取り組みが進められています。本稿では「コンパクトシティとは何か」「山口県の現状」「採れる政策・実務的な手立て」「現実的な課題と可能性」を事実に基づいて整理します。結論めいた一言を先に言うと――「可能性はある。ただし地域ごとの実情に即した段階的・ネットワーク的な進め方が肝心」です。以下、根拠を示しながら解説します。
1)コンパクトシティとは?国の考え方
コンパクトシティは、「住まい・医療・福祉・買物・交通などの都市機能を市街地へ集約し、公共交通でつながる持続可能な都市構造」を目指す考え方です。国(国土交通省など)は、立地適正化計画や地方創生交付金などで市町村の取り組みを支援しています。具体策は「居住誘導」「中心市街地の再整備」「交通ネットワークの再構築」などに分かれます。国土交通省+1
2)山口県の現状
山口県は少子高齢化と人口減少の影響が長期的に見込まれており、県の将来推計でも高齢化の進展が示されています(県の将来推計・分析資料)。山口県公式サイト
空き家の問題が顕著で、令和5年(2023年)の住宅・土地統計では山口県の空き家率は約19.4%で、全国平均を上回る状況です(空き家戸数・率の県公表)。これはまちの機能分散・維持費負担の重さと直結します。山口県公式サイト+1
これらはコンパクトなまちづくりを考える大きな動機になります:都市機能を絞り、空き家を整理・再利用して暮らしやすさを守る必要がある、ということです。
3)山口県での取り組み
山口県は「コンパクトなまちづくりモデル事業」を設け、市町と協働してモデル地区での実証・支援を行っています。県の公式ページにはモデル地区の経緯や取組状況が掲載されています。山口県公式サイト
また、防府市や柳井市などで「立地適正化計画(居住誘導や都市機能誘導の計画)」を策定・公表しており、個別市町で実務に落とす動きが出ています。山口県公式サイト+1
これらは「県・市町が方針を持って進める体制」が整いつつある証拠で、コンパクト化のための制度的・予算的支援の道筋もあります。
4)現実的な課題
地理的条件と自治体数:山口県は沿岸線が長く、山地も多い。小さな市町村が多く、単独で全面的なコンパクト化を進めるのは難しい(交通網・医療機能の確保の面で非効率)。
公共交通の維持:地方ほど公共交通は採算が取りにくく、コンパクト化は交通整備(デマンド交通や路線再編)とセットでないと住民の移動が困難になります。国の支援制度やデマンド型導入が鍵です。国土交通省+1
空き家・住宅ストックの扱い:単に空き家を取り壊すのではなく、リノベや賃貸化、若年・子育て世代の誘導など「受け皿」を作る必要があります。山口県公式サイト
住民合意と地方財政:コンパクト化はインフラや施設の集約を伴うため、住民説明・合意形成や長期的な財政計画が不可欠です。山口県公式サイト
5)実践的に「可能」にするための戦略
拠点+ネットワーク(コンパクト+ネットワーク)
山口県のように市町村が分散するエリアでは、地域ごとの「生活拠点」を明確にし、拠点間を公共交通や連携サービスで結ぶ考え(コンパクト+ネットワーク)が有効。国・県のガイドラインや支援もこの方向を示しています。国土交通省の国土技術政策総合センター+1
山口県のように市町村が分散するエリアでは、地域ごとの「生活拠点」を明確にし、拠点間を公共交通や連携サービスで結ぶ考え(コンパクト+ネットワーク)が有効。国・県のガイドラインや支援もこの方向を示しています。国土交通省の国土技術政策総合センター+1
立地適正化計画の推進と実行フェーズの設計
市町が立地適正化計画を作り、誘導区域を定めて住宅・福祉・商業の立地調整を行う—その後、具体的な施設移転支援や空き家流通施策(補助、リノベ支援、空き家バンク)を組むこと。山口県内でも既に計画策定の事例があります。山口県公式サイト+1
市町が立地適正化計画を作り、誘導区域を定めて住宅・福祉・商業の立地調整を行う—その後、具体的な施設移転支援や空き家流通施策(補助、リノベ支援、空き家バンク)を組むこと。山口県内でも既に計画策定の事例があります。山口県公式サイト+1
公共交通の再編
採算性が低い路線は、住民の需要に応じたデマンド型交通や、隣接自治体との共同運行で効率化。国の補助が利用できる場合もあるので、自治体が補助制度を積極的に活用する。国土交通省+1
採算性が低い路線は、住民の需要に応じたデマンド型交通や、隣接自治体との共同運行で効率化。国の補助が利用できる場合もあるので、自治体が補助制度を積極的に活用する。国土交通省+1
空き家の「資産化」
空き家を壊すだけでなく若年層やリモートワーカー向けリノベ、サテライトオフィス、観光寄与型宿泊など用途多様化で活用。県の空き家実態を踏まえ、事業化できる案件を見極める必要があります。山口県公式サイト
空き家を壊すだけでなく若年層やリモートワーカー向けリノベ、サテライトオフィス、観光寄与型宿泊など用途多様化で活用。県の空き家実態を踏まえ、事業化できる案件を見極める必要があります。山口県公式サイト
6)成功の“分かれ目”
地域ごとのアセスメント(医療・買物・交通の最短アクセス)を数値で示すこと(説得力のある根拠が住民合意を生む)山口県公式サイト
県・国の補助を設計段階から取り込むこと(費用負担の軽減と実行力)国土交通省
複数自治体での連携(サービス共有)――単独ではなくネットワークで持続可能なモデルを作る。国土交通省の国土技術政策総合センター
まとめ:山口県での可否判定
データ(人口推計・空き家率)や県の既存事業を見ると、「やらないとまずい」段階にあることは明らかです。県・市町は既にモデル事業や立地適正化計画の作成で動いており、国の支援策もあります。よって「不可能」ではなく「実現には計画と連携・段階的実行が不可欠」――が結論です。山口県公式サイト+2山口県公式サイト+2
おわりに
まちの未来を考えるとき、不動産のプロ・行政・住民が同じテーブルに座ることが必要です。もし自治体や地元事業者に関わる立場なら、まずは「市町単位の立地適正化計画と拠点アセスメント」を進め、県のモデル事業や国の補助の活用を検討してみてください。市民として関わるなら、計画説明会に参加して「生活動線」を示すことが大きな力になります。山口県公式サイト+1
参考(主要出典)
山口県「山口県のコンパクトなまちづくり」ページおよびモデル事業紹介。山口県公式サイト+1
国土交通省 等:コンパクトシティ政策パッケージ(立地適正化計画や支援策)。国土交通省+1
山口県統計・将来推計(県の推計資料)。山口県公式サイト
山口県の空き家に関する県公表データ(住宅・土地統計調査の県まとめ)。