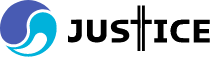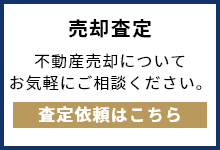収益還元法の闇――数字の魔法に隠れた落とし穴
不動産投資や収益物件の売買の場面で必ず登場するのが「収益還元法」。
「この物件は年間○○万円の家賃収入が見込めるから、利回り△%で計算すると価値は□□万円」――
「この物件は年間○○万円の家賃収入が見込めるから、利回り△%で計算すると価値は□□万円」――
そんな説明を耳にしたことがある方も多いのではないでしょうか。
一見シンプルでわかりやすいこの評価方法ですが、実は**“闇”とも言える落とし穴**があります。
今日は不動産業界の裏側を少しのぞいてみましょう。
そもそも収益還元法とは?
収益還元法とは、物件が将来生み出す収益(賃料や運営益)を基に、不動産の現在価値を算出する方法です。
大きく分けて2種類があります。
大きく分けて2種類があります。
直接還元法:
1年間の純収益 ÷ 還元利回り = 価格
1年間の純収益 ÷ 還元利回り = 価格
DCF法(ディスカウント・キャッシュフロー法):
将来の複数年にわたる収益を割り引いて合計し、価格を算出
将来の複数年にわたる収益を割り引いて合計し、価格を算出
金融商品的な発想を不動産に持ち込んだ合理的な評価法と言えます。
「闇」が潜むポイント
では、どこに“闇”があるのでしょうか?代表的なポイントを挙げます。
① 利回り設定は“人の手”で変わる
収益還元法は「利回り」をどう設定するかで大きく数字が変わります。
利回りを低く設定すれば価格は跳ね上がり、逆に高く設定すれば価格は下がる。
つまり**同じ物件でも評価者の意図次第で“高くも安くも見える”**のです。
利回りを低く設定すれば価格は跳ね上がり、逆に高く設定すれば価格は下がる。
つまり**同じ物件でも評価者の意図次第で“高くも安くも見える”**のです。
利回りを低く設定した場合の例
1年間の純収益が100万円で、還元利回りを4%に設定した場合:100万円 ÷ 4% = 2,500万円
この場合、投資家は2,500万円で購入しても4%の利回りが得られます。
利回りを高く設定した場合の例
1年間の純収益が同じ100万円で、還元利回りを5%に設定した場合:100万円 ÷ 5% = 2,000万円
この場合、投資家は2,000万円で購入しても4%の利回りが得られます。
② 将来収益の予測は不確実
「今の家賃が続く」と仮定して計算されることが多いですが、実際には…
空室が発生する
家賃相場が下落する
修繕コストがかかる
といったリスクがあります。
予測は都合よく作られることが多いため、机上の数字と現実の乖離が問題になります。
といったリスクがあります。
予測は都合よく作られることが多いため、机上の数字と現実の乖離が問題になります。
③ 投資家心理を利用した“魅せ方”
販売図面や投資セミナーでよくあるのが、
「利回り○%! 今だけ高収益!」といったキャッチコピー。
しかしその裏では、実際には一時的な家賃保証や空室対策費を無視して計算しているケースもあります。
見かけの利回りに安心して飛びつくと、数年後に手残りが全く違う、という事態に。
「利回り○%! 今だけ高収益!」といったキャッチコピー。
しかしその裏では、実際には一時的な家賃保証や空室対策費を無視して計算しているケースもあります。
見かけの利回りに安心して飛びつくと、数年後に手残りが全く違う、という事態に。
収益還元法とどう付き合うべきか?
「闇」があるから使えないわけではありません。むしろ、収益不動産の評価に欠かせない考え方です。大切なのは数字の裏を読む視点です。
利回りの根拠は何か?(周辺事例か、恣意的な設定か)
家賃収入は実績か?将来の希望的観測か?
ランニングコスト(修繕費・管理費・税金)はきちんと織り込まれているか?
これらを一つひとつ検証することで、表面だけの“数字の魔法”に惑わされなくなります。
まとめ
収益還元法は投資家にとって強力なツールですが、同時に「数字をどう見せるか」で評価が変わる危うさをはらんでいます。
素人でも「利回りの根拠」や「将来収益の現実性」を意識して見れば、不動産の実態をより正しく理解できるでしょう。
素人でも「利回りの根拠」や「将来収益の現実性」を意識して見れば、不動産の実態をより正しく理解できるでしょう。
「収益還元法の闇」を知っているかどうかで、あなたの投資判断は大きく変わります。