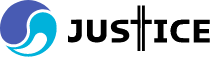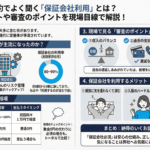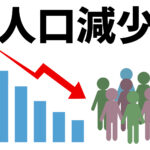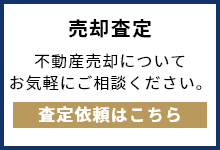成年後見制度とは? 不動産取引にも影響する制度のメリットとデメリットを解説
「高齢の親が判断力を失ってしまったら、不動産を売ったり管理したりできなくなるの?」
そんな不安を抱えるご家族に知ってほしいのが【成年後見制度】です。
そんな不安を抱えるご家族に知ってほしいのが【成年後見制度】です。
近年、認知症の高齢者が増加する中で、不動産売買や管理においてこの制度の重要性が増しています。
この記事では、不動産に関わる視点から「成年後見制度とは何か?」をわかりやすく解説し、
制度のメリットとデメリットを整理します。
成年後見制度とは?
成年後見制度は、判断能力が不十分な方(例:認知症、知的障がい、精神障がいなど)を法律的にサポートする制度です。
家庭裁判所が選任した「後見人」が、本人の代わりに財産の管理や契約などを行います。
家庭裁判所が選任した「後見人」が、本人の代わりに財産の管理や契約などを行います。
この制度は、2000年に施行された【成年後見制度(民法第7条・第876条以下)】に基づいて運用されています。
成年後見制度の種類
成年後見制度には、主に以下の2つのタイプがあります。
| 制度名 | いつ利用する? | 主な対象 |
|---|---|---|
| 法定後見制度 | すでに判断能力が低下した後に開始 | 認知症の高齢者など |
| 任意後見制度 | 元気なうちに将来に備える契約 | 高齢者・障がい者など |
不動産業における「後見制度」の必要性とは?
判断能力がない状態では、本人による不動産の売買契約は無効です。
例えば——
空き家になった実家を売却したい
施設入居にあたり自宅を賃貸に出したい
こうした場面で、本人が契約できない=取引ができないという事態が生じます。
その際に、「成年後見制度」を利用することで、後見人が代わって契約や登記手続きを行えるようになります。
その際に、「成年後見制度」を利用することで、後見人が代わって契約や登記手続きを行えるようになります。
メリット:制度を使うことで得られる安心
法的に有効な契約が可能
→ 不動産の売却・賃貸契約が有効に成立する。
→ 不動産の売却・賃貸契約が有効に成立する。
本人の財産を守れる
→ 後見人が裁判所の監督下で管理。使い込みや詐欺から保護。
→ 後見人が裁判所の監督下で管理。使い込みや詐欺から保護。
家族間トラブルの回避
→ 誰が何を決めるかが制度上明確になり、兄弟姉妹間での争いを防ぐ効果も。
→ 誰が何を決めるかが制度上明確になり、兄弟姉妹間での争いを防ぐ効果も。
デメリット:知っておきたい注意点
手続きが煩雑で時間がかかる
→ 家庭裁判所への申立てから開始まで、平均2〜3ヶ月以上。
→ 家庭裁判所への申立てから開始まで、平均2〜3ヶ月以上。
裁判所の監督が続く
→ 後見人は定期的に報告義務があり、自由に売買できないケースも。
→ 後見人は定期的に報告義務があり、自由に売買できないケースも。
費用がかかる
→ 申立て費用(1〜3万円程度)+鑑定費用(5〜10万円程度)
さらに、専門職後見人(弁護士・司法書士)が選任された場合、毎月2〜5万円の報酬がかかる。
→ 申立て費用(1〜3万円程度)+鑑定費用(5〜10万円程度)
さらに、専門職後見人(弁護士・司法書士)が選任された場合、毎月2〜5万円の報酬がかかる。
不動産取引での実例:「親の家を売れない」事態を防ぐために
あるご相談では、認知症を患った母親の代わりに、息子さんが実家を売却しようとしましたが、本人の署名捺印がない契約書は無効と判断され、取引ができませんでした。
→ 結果的に、家庭裁判所へ成年後見制度を申し立て、後見人が売主となって契約が成立。
しかし、制度利用開始まで約4ヶ月かかり、買主から「遅い」と断られた物件もありました。
しかし、制度利用開始まで約4ヶ月かかり、買主から「遅い」と断られた物件もありました。
まとめ:備えあれば憂いなし
成年後見制度は、本人の権利を守りながら、不動産取引の「出口」を開く大切な制度です。
しかし、制度の特性を理解せずに進めると、取引の遅延や思わぬ出費につながることも。
しかし、制度の特性を理解せずに進めると、取引の遅延や思わぬ出費につながることも。
不動産に関わる方こそ、「もしもの備え」として制度を正しく理解しておくことが大切です。
元気なうちからの【任意後見契約】も視野に入れて、専門家(司法書士や弁護士)への早めの相談をおすすめします。
元気なうちからの【任意後見契約】も視野に入れて、専門家(司法書士や弁護士)への早めの相談をおすすめします。