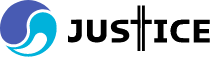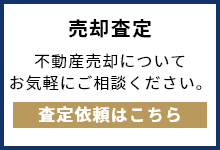休耕田畑への太陽光パネル設置——その未来に希望はあるのか?
こんにちは、
今回は、地方で増え続ける「休耕田や耕作放棄地」に焦点を当てながら、そこに太陽光発電を導入する動きについて、メリット・デメリットを踏まえた上で、私たちの暮らしと未来にどう関わるかを深掘りしていきます。
🌱 そもそも「休耕田」って何?
「休耕田」とは、一時的に作物を育てるのをやめた農地のこと。高齢化や後継者不足、農業の収益性低下などが原因で、全国的に増えています。
実際、農林水産省によると、2020年時点で耕作放棄地は全国で約42万ヘクタール(東京都の2倍以上)にも及びます。
実際、農林水産省によると、2020年時点で耕作放棄地は全国で約42万ヘクタール(東京都の2倍以上)にも及びます。
☀️ なぜ今、そこに太陽光パネル?
使われなくなった土地を活用して、再生可能エネルギーを生み出すというアイデアは、一見すると「いいことづくし」に見えますよね。でも、ほんとうにそうなのでしょうか?
✅ メリット:いいこと、実はけっこうある!
1. 土地の有効活用
放置して草が生い茂るだけの土地が、エネルギーを生み出す発電所に変身。これは所有者にとっても、地域にとっても価値のある再生です。
2. 安定収入につながる
個人でも企業でも、発電した電気を売電できる仕組みが整っており、10〜20年スパンの安定収入が期待されます。
3. 環境への貢献
CO₂を出さないクリーンなエネルギーとして、地域の脱炭素化に貢献。国のグリーン政策とも相性バッチリ。
❌ デメリット:見落としてはいけない問題点
1. 農地法の壁
農地をそのまま発電所に転用するには、「農地転用」の許可が必要。条件も厳しく、申請も面倒。
2. 景観や環境への影響
地域によっては「太陽光パネルばかりの風景」に住民が違和感を感じることも。土砂災害や水害リスクを高める事例も報告されています。
3. 20年後、残るのは…?
多くの発電事業は20年で売電契約が終了。その後、誰が撤去費用を負担するのか、曖昧なまま放置されるリスクがあります。
🌀 実はトラブルも増えている
2020年代に入り、ずさんな施工や管理不全の太陽光施設が問題視されるようになりました。
例えば、「地元に説明もなく、いつの間にか発電所ができていた」「台風でパネルが飛んできた」といった声も。
例えば、「地元に説明もなく、いつの間にか発電所ができていた」「台風でパネルが飛んできた」といった声も。
🌍 それでも、未来はある?
実は最近、「ソーラーシェアリング(営農型太陽光発電)」という新しい考え方が注目されています。
これは、作物を育てながら、上空に太陽光パネルを設置する方法。農業と再生可能エネルギーの“いいとこ取り”ですね。
これは、作物を育てながら、上空に太陽光パネルを設置する方法。農業と再生可能エネルギーの“いいとこ取り”ですね。
▼たとえば…
葉物野菜などは“日陰”でも育つ
太陽光パネルが日射を和らげて、夏場の猛暑対策にも
📝 まとめ:未来をつくるのは、土地の“使い方”次第
✔ 放置するよりは何かに活かしたい
✔ ただし、安易な導入は逆効果にもなる
✔ 「営農型」「地域連携型」など、新しい発想がカギ
日本中に点在する“使われなくなった農地”。そこをどう活かすかは、私たち一人ひとりの想像力と行動力にかかっています。