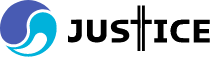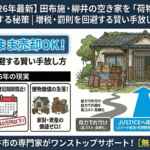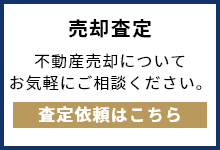地下40メートル以深は誰のものでもない?
―地面の下の「見えない領域」に広がる法律と未来の話―
「自分の土地は空の上から地面の下まで全部、自分のものだと思っていました…」
不動産や土地の所有に関して、こうした「常識」だと思っていたことが、実は法律的にはそうでもない――そんな“学びのタネ”になるテーマが、今回の「地下40メートル問題」です。
では、あなたの土地の“地下深く”は、誰のものなのでしょうか?
◆ 地下40メートル以深は「誰のものでもない」?
これは法律上、実際にこう明記されているわけではありませんが、「ある判例」と「現在の法律の運用」から、通称的にそう呼ばれるようになったものです。
民法第207条にはこうあります。
土地の所有権は、法令の制限内において、その土地の上下に及ぶ。
つまり、「土地の上下も含めて自分のもの」ではあるものの、「法令の制限」が付くという条件があります。
この“制限”の考え方が重要なのです。
◆ なぜ40メートル?根拠は何?
実は「地下40メートルより深い部分」は、地上の生活や経済活動に直接関係しない“超深度”として、所有権の主張が認められにくい領域とされています。
これは、2001年に施行された「大深度地下の公共的使用に関する特別措置法(通称:大深度法)」がきっかけです。
この法律では、地下40メートル以深の空間について、一定の条件を満たせば「土地所有者の同意がなくても公共目的でトンネルなどの構築が可能」とされました。
つまり、40メートルを超えるような“深さ”は、もう個人の土地の一部とまでは言えない、という扱いになったのです。
◆ 実際に何が起きている?
たとえば、東京外環道(外郭環状道路)やリニア中央新幹線では、地下40メートル以深にトンネルを通す計画が実際に進んでいます。
その際には、従来であれば土地の所有者一人ひとりに同意を取る必要がありましたが、大深度法の適用により「一定の公共性と安全性が確保されていれば、手続きを簡略化できる」ようになりました。
これにより、都市開発や交通インフラの効率化が図られているのです。
◆ それって“勝手に掘っていい”ってこと?
決してそういうわけではありません。
大深度法が適用されるには、国の認可が必要であり、「誰でも自由に掘っていい」「好きに地下ビジネスができる」わけではありません。
さらに、地震の影響、地盤沈下、環境リスクなども慎重に審査されます。
◆ 地下空間は「未来の資源」?
近年は地下におけるデータセンター、物流トンネル、避難空間などの活用も注目されています。
都市の過密化が進む中、空だけでなく「地下空間」も新たなフロンティアとして見直されているのです。
「地下40メートル以深は誰のものでもない」と言えるなら、それは“誰でも使える可能性がある空間”としても捉えられる――未来の都市構想に関わる大きなテーマでもあります。
◆ まとめ:あなたの土地、地下はどこまで“あなたのもの”?
結論としては、
土地の上下は所有者のものだが、
一定の深さ(40メートル以深)を超えると、
公共目的で使用される場合、所有者の権利は及ばないこともある。
というのが、現在の法的な考え方です。
普段意識することのない「地面の下」も、実は都市と法律と技術が交錯する“もうひとつの世界”。
身近な土地の話から、地下都市やリニア新幹線まで。
少し視点を変えると、不動産の世界はこんなにも広く、深いのです。
少し視点を変えると、不動産の世界はこんなにも広く、深いのです。