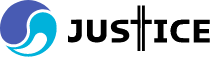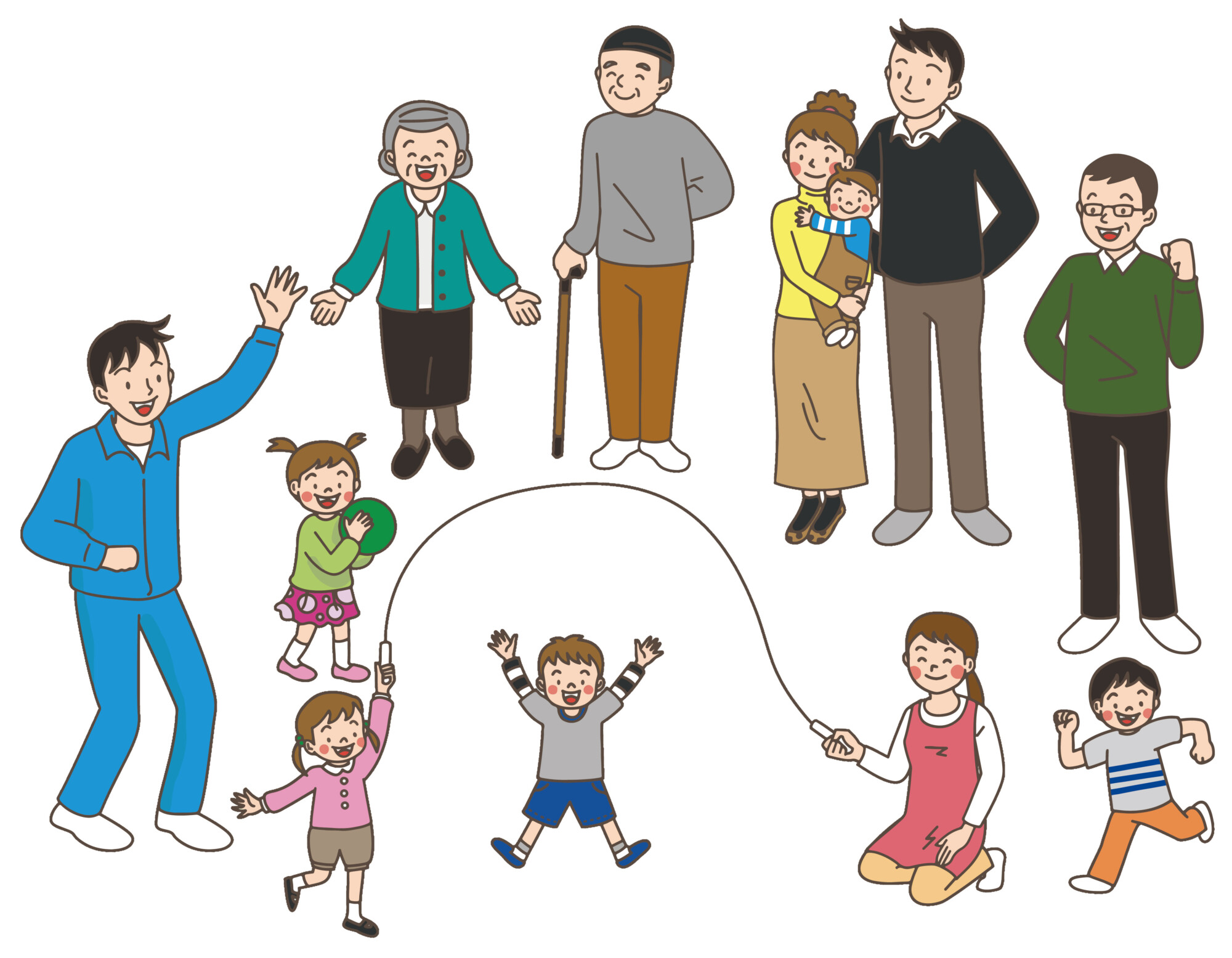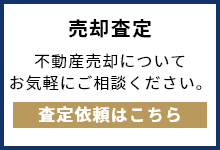「その契約、ホントに有効?―知っておきたい“公序良俗”の壁」
1. 公序良俗って、なに?
「公序良俗(こうじょりょうぞく)」と聞いて、ピンとくる人は少ないかもしれません。
でも実は、私たちの暮らしの中でこの言葉、とっても大事なんです。
でも実は、私たちの暮らしの中でこの言葉、とっても大事なんです。
法律的には、「公共の秩序」や「善良な風俗」に反することを禁止するルールのこと。
つまり、社会の常識やモラルに反するような契約は、たとえ紙にサインしていても“無効”になる、というわけです。
つまり、社会の常識やモラルに反するような契約は、たとえ紙にサインしていても“無効”になる、というわけです。
たとえば…
「暴力団にみかじめ料を払う契約」
「不倫関係の解消を条件に高額な慰謝料を払う約束」
「人身売買まがいの労働契約」
こんな契約は、すべて“公序良俗違反”として、裁判でも無効になります。
2. 実は身近な“アウト契約”
たとえば不動産業界でも、こんなケースがあります。
■ケース1:「この部屋は外国人には貸しません」という契約条項
→ 差別的内容として、公序良俗違反になる可能性大。
→ 差別的内容として、公序良俗違反になる可能性大。
■ケース2:連帯保証人に全財産を差し出す内容の過剰な保証契約
→ 近年、最高裁判例でも無効とされたことがあります。
→ 近年、最高裁判例でも無効とされたことがあります。
つまり、たとえ当事者が納得して契約していても、“社会常識に反していれば無効”になる可能性があるということです。
3. なぜ“公序良俗”が守られるのか?
社会はルールがあってこそ成り立ちます。
契約自由の原則がある一方で、それが“社会の安全”や“人間としての尊厳”を損なうものであってはならないという基本的な考え方があるのです。
契約自由の原則がある一方で、それが“社会の安全”や“人間としての尊厳”を損なうものであってはならないという基本的な考え方があるのです。
公序良俗は、いわば「契約社会のブレーキ装置」。
個人の自由を守りながら、社会全体の秩序を守るために機能しています。
個人の自由を守りながら、社会全体の秩序を守るために機能しています。
4. 知っておくべきサイン―こんなときは要注意!
内容が極端に一方的
相手が社会的に弱い立場(未成年、外国人、高齢者など)
「誰にも言わないで」と言われた
常識的に考えて不自然
こんな契約には、公序良俗違反の可能性があります。
5. まとめ:契約書を交わす前に「これってモラル的にどう?」と立ち止まろう
公序良俗は、契約における“見えないルールブック”のようなもの。
サインをする前に「これって常識に反していないかな?」と自分の中で確認する習慣を持つだけで、リスクを大きく減らすことができます。
サインをする前に「これって常識に反していないかな?」と自分の中で確認する習慣を持つだけで、リスクを大きく減らすことができます。
📌 おまけ:知って安心!
不安な契約内容があったら、消費者センターや弁護士、不動産会社など、専門家に一度相談を。
不安な契約内容があったら、消費者センターや弁護士、不動産会社など、専門家に一度相談を。