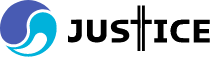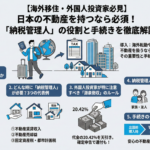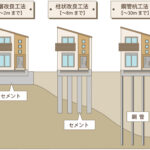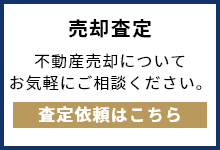相続放棄したのに空き家の管理責任はあるの?
はじめに
「親の家を相続放棄したのに、空き家の管理をしろと言われた…」
実際にこうした声を耳にすることがあります。
相続放棄をすれば財産も負債も一切関係なくなる――そう思いがちですが、
実際にこうした声を耳にすることがあります。
相続放棄をすれば財産も負債も一切関係なくなる――そう思いがちですが、
民法上は一定の範囲で「管理責任」が残る場合があるのです。
この記事では、2024年4月に施行された民法改正を踏まえながら、相続放棄と空き家の管理責任についてわかりやすく解説します。
相続放棄とは?
相続放棄とは、被相続人(亡くなった方)の財産も借金も一切相続しないという選択です。
家庭裁判所に「相続放棄の申述」を行い、受理されることで初めて法的に効力が生じます。
家庭裁判所に「相続放棄の申述」を行い、受理されることで初めて法的に効力が生じます。
相続放棄をすれば、原則としてその財産に対して何の権利も義務もなくなるのが基本です。
しかし――ここに「空き家問題」が絡むと話が少し複雑になります。
しかし――ここに「空き家問題」が絡むと話が少し複雑になります。
相続放棄しても一時的に「管理義務」は残る
相続放棄をしても、放棄の効力が確定するまでの間は、相続人としての地位を一時的に持っているとみなされます。
このため、民法940条により
「相続人は、相続財産の管理をしなければならない」
とされています。
とされています。
つまり、相続放棄をしたからといって、すぐに「空き家の管理から完全に解放される」わけではないのです。
2024年4月の民法改正で明確化された点
従来の法律では、「放棄しても管理義務があるのかどうか」が曖昧で、自治体や近隣住民との間でトラブルになるケースがありました。
しかし、2024年4月施行の**民法改正(相続制度の見直し)**により、次のように明確化されました。
✅ 相続放棄者が被相続人の財産を現に占有していない場合、管理義務は負わない。
つまり、実際にその家に住んでいなかったり、鍵を預かっていないなど、事実上の支配をしていない場合には責任がないということが法律でハッキリ定められたのです。
それでも注意が必要なケース
とはいえ、すべてのケースで「放棄すれば終わり」とは限りません。
●① 放棄後も家の管理を続けた場合
放棄後も掃除をしたり、空き家の鍵を保管していたりすると、実質的に管理しているとみなされるおそれがあります。
その場合、倒壊や火災などで損害が生じた際には、管理責任を問われる可能性があります。
その場合、倒壊や火災などで損害が生じた際には、管理責任を問われる可能性があります。
●② 行政からの「勧告」や「代執行」
空き家が著しく危険な状態にあると、自治体は「特定空家等」として是正を求めることができます。
放棄者が管理しているように見える場合、勧告や命令の対象になることもありえます。
放棄者が管理しているように見える場合、勧告や命令の対象になることもありえます。
放棄後の安全な対応ステップ
| ステップ | 対応内容 |
|---|---|
| ① | 相続放棄の申述を家庭裁判所に正式に行う |
| ② | 放棄後は物件の鍵・書類などを他の相続人や相続財産管理人に引き渡す |
| ③ | 現地に出入りせず、管理も行わないようにする |
| ④ | 可能であれば、裁判所に相続財産管理人の選任を申し立てて、正式に管理を任せる |
このように手続きをきちんと踏むことで、「相続放棄後の管理責任」から安全に離れることができます。
まとめ
相続放棄をしても、放棄の効力が確定するまでは管理義務が残る
しかし2024年4月の民法改正で、現に占有していない場合は管理義務を負わないと明確化された
放棄後も実質的な管理行為をすれば、責任を問われる可能性がある
トラブルを避けるには、相続財産管理人の選任を検討することが安全
最後に
相続放棄をしても「空き家問題」は残ります。
しかし、法改正により責任の範囲が明確になった今、正しい手続きを踏めば不安を減らすことができます。
しかし、法改正により責任の範囲が明確になった今、正しい手続きを踏めば不安を減らすことができます。
不動産や相続で悩んだときは、早めに専門家(司法書士・弁護士・不動産業者)に相談することが何よりの安心です。