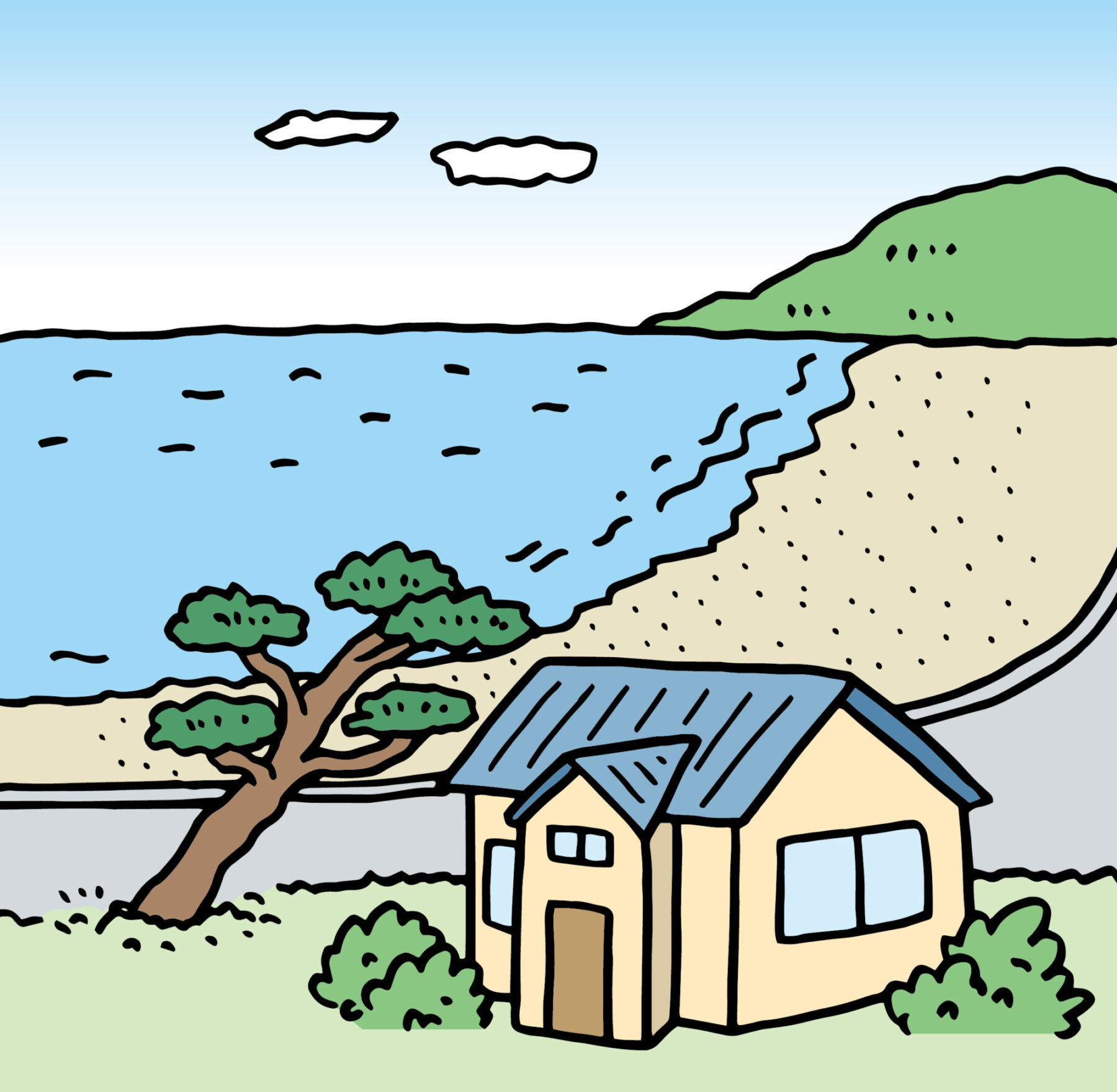はじめに
「海の見える家に住みたい」「海のそばでカフェを開きたい」──
そんな憧れを持つ方も多いのではないでしょうか。
そんな憧れを持つ方も多いのではないでしょうか。
けれども、海の近くの土地には、一般の住宅地とは少し違う法律上のルールがあります。
そのひとつが 「海岸法(かいがんほう)」 です。
そのひとつが 「海岸法(かいがんほう)」 です。
この記事では、これから海沿いの不動産を探す方に向けて、
海岸法とは何か、どんな影響があるのかを、やさしく説明します。
海岸法とは何か、どんな影響があるのかを、やさしく説明します。
海岸法ってどんな法律?
海を守り、人を守るためのルール
「海岸法」とは、昭和31年(1956年)にできた国の法律です。
目的はシンプルで、
海岸の侵食や高潮、津波などによる災害を防ぎ、人々の命や財産を守ること。
つまり、海辺の安全を守るためのルールなのです。
「海岸保全区域」という特別なエリア
海のそばの土地は“守るべき区域”に指定されることがある
海岸法では、都道府県知事が必要と判断した場所を「海岸保全区域」に指定します。
この区域では、
建物を建てる
土地を盛ったり削ったりする
樹木を伐採する
といった行為をする場合に、県の許可が必要になります。
といった行為をする場合に、県の許可が必要になります。
無許可で行うと、工事を止められたり、原状回復を命じられることもあります。
山口県ではどんな場所が対象?
山口県は日本海と瀬戸内海の両方に面しており、海岸線の長さは約1,500kmもあります。
このうち、約4分の1が「海岸保全区域」に指定されています。
このうち、約4分の1が「海岸保全区域」に指定されています。
たとえば次のような場所が該当します。
萩市・長門市エリア(日本海側):
台風や高波の影響を受けやすく、防潮堤や護岸が整備された区域。
台風や高波の影響を受けやすく、防潮堤や護岸が整備された区域。
周防大島町・下松市笠戸島(瀬戸内海側):
景観と自然を守るための「自然海浜保全地区」に指定された砂浜もあります。
景観と自然を守るための「自然海浜保全地区」に指定された砂浜もあります。
こうした区域では、たとえ個人の所有地でも、
建物を建てる際は事前に県土木事務所などへの確認が必要になります。
建物を建てる際は事前に県土木事務所などへの確認が必要になります。
登記簿には書いていない「見えない制限」
多くの方が勘違いしやすいのがここです。
海岸保全区域の指定は、登記簿や固定資産税の資料には載っていません。
つまり、土地の名義を見ても分からないのです。
つまり、土地の名義を見ても分からないのです。
購入を検討するときは、必ず次のように確認してください。
「この土地は海岸保全区域に入っていますか?」
県や市町の建設課・港湾課・土木事務所で調べてもらえます。
建てられないわけではないが「制限つき」
海岸保全区域に入っているからといって、
必ずしも「家が建てられない」というわけではありません。
必ずしも「家が建てられない」というわけではありません。
ただし、
建物の高さや構造
地盤の掘削深さ
護岸からの距離
などについて、県の許可や条件が付くことがあります。
などについて、県の許可や条件が付くことがあります。
これは、高潮や浸水などの災害を防ぐためのものです。
海沿いの土地を検討する前に知っておきたい3つのポイント
① まずは「区域指定」を確認
土地が海岸保全区域に含まれるかどうかを調べることが第一歩。
不動産会社や県の担当窓口に確認しましょう。
不動産会社や県の担当窓口に確認しましょう。
② 許可が必要な行為を知っておく
建物を建てる、塀を作る、土地を造成する──
これらは海岸保全区域では事前許可制です。
これらは海岸保全区域では事前許可制です。
③ 災害リスクも合わせて考える
海のそばは景観が魅力ですが、高潮・津波などの自然リスクもあります。
ハザードマップの確認も忘れずに。
ハザードマップの確認も忘れずに。
まとめ:海を楽しむ暮らしのために「法のルール」を知っておこう
海のそばの暮らしは魅力的ですが、
「海岸法」という見えないルールを理解しておくことが、安全で安心な生活につながります。
「海岸法」という見えないルールを理解しておくことが、安全で安心な生活につながります。
まずは土地を購入する前に、「その場所がどんな区域にあるのか」を確認すること。
それが、後悔しない不動産購入の第一歩です。