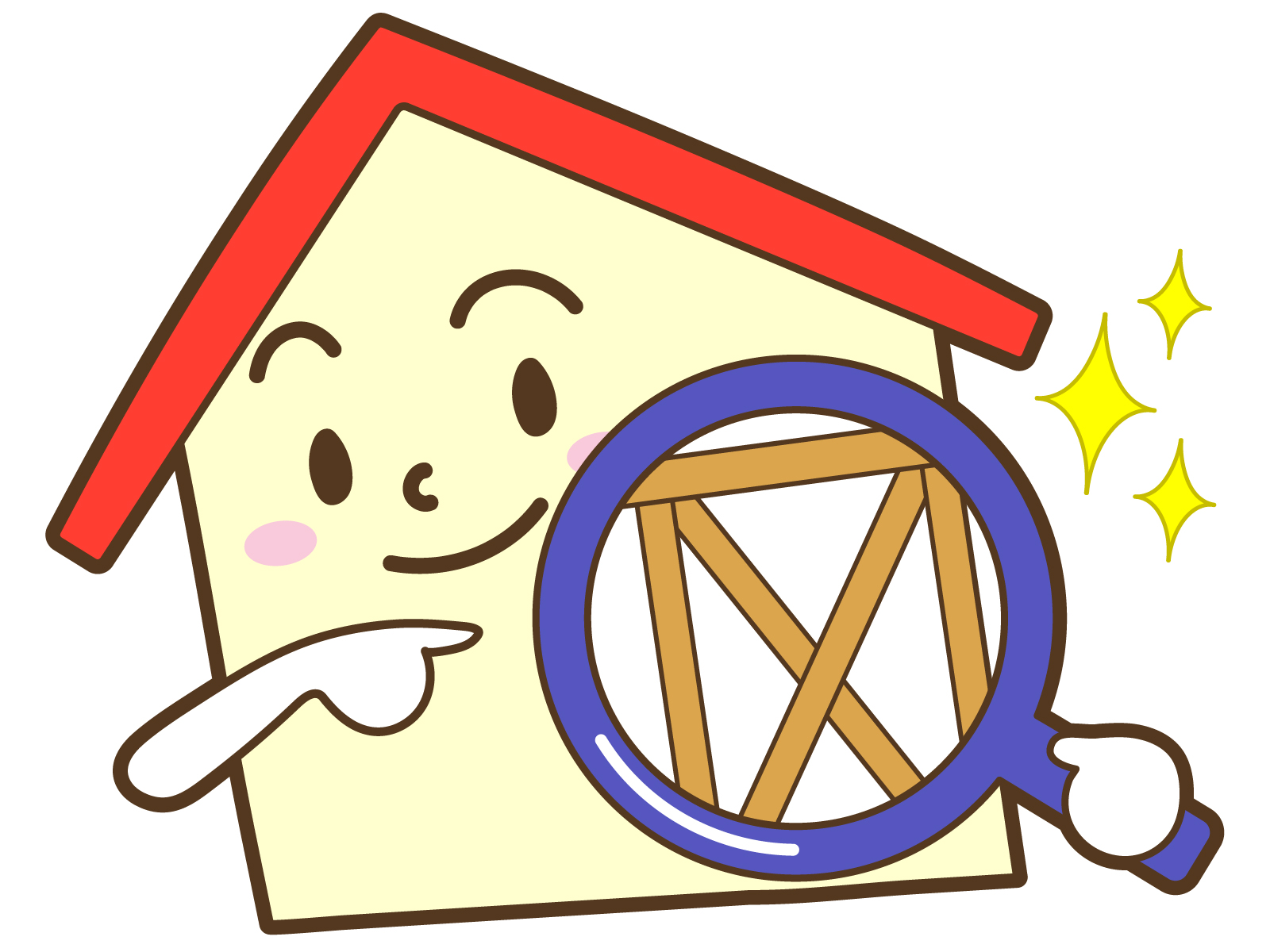「実家のある田舎に空き家が残っていて、どうしたものか悩んでいる」
「田舎暮らしにあこがれるけど、古い家の安全性が心配」
そんな声を最近よく耳にします。
「田舎暮らしにあこがれるけど、古い家の安全性が心配」
そんな声を最近よく耳にします。
特に日本の地方、いわゆる“過疎地”では、築年数の経った住宅が多く残されています。これらの家は、味のある木造建築であったり、広い敷地を備えていたりと、都市部では得がたい魅力がありますが、一方で耐震性が心配されることもしばしば。
今回は、「過疎地の住宅」と「耐震性」という2つのテーマを軸に、「古民家って本当に危ないの?」「耐震補強って何をすればいいの?」といった素朴な疑問にお答えしながら、地域の家を未来につなげていくヒントをご紹介します。
■ 古い家=危険?それとも、価値ある資産?
1981年以前に建てられた住宅は「旧耐震基準」と呼ばれる、現在の基準よりもゆるやかな耐震設計のもとに建てられています。そのため、過疎地に多い昭和中期の住宅は、耐震性能に課題を抱えていることが少なくありません。
しかし一方で、これらの住宅は良質な木材で建てられていたり、匠の技術が生かされていたりと、構造的なポテンシャルは非常に高いこともあります。適切な点検と補強で、安全に生まれ変わる可能性も十分あるのです。
■ 耐震補強って、どれくらい大変?
「耐震補強」と聞くと、大がかりな工事を想像して身構えてしまう方も多いかもしれません。ですが、すべての家に莫大な費用がかかるわけではありません。
まずは専門家による「耐震診断」からスタート。自治体によっては、この診断や補強工事に対して補助金が出るケースもあります。
具体的な補強の内容としては、
壁の筋交い(すじかい)追加
土台や柱の接合部の補強
屋根の軽量化
などがあり、家全体のバランスを見ながら行います。
などがあり、家全体のバランスを見ながら行います。
■ 地方だからこそ活きる「安心+広さ+自然」
都会での生活に疲れた人が、自然豊かな地方での暮らしに目を向ける流れは年々強まっています。
そんな中で「安心して住める」住宅の確保は、地域への移住促進にもつながる大きなポイントです。
そんな中で「安心して住める」住宅の確保は、地域への移住促進にもつながる大きなポイントです。
空き家や古民家を耐震補強して活用すれば、「趣のある家に、安心して暮らす」という、まさに理想的な生活が実現できます。
また、家族の安全を守ることはもちろん、将来子や孫へ“住まい”を受け継ぐ大きな財産にもなります。
また、家族の安全を守ることはもちろん、将来子や孫へ“住まい”を受け継ぐ大きな財産にもなります。
■ まとめ:地域の家を未来につなぐ第一歩
過疎地の古い家は、ただの「問題」ではなく、「可能性の宝庫」です。
耐震性の不安があるなら、まずは調べて、知って、向き合うこと。
専門家に相談すれば、意外と現実的な手段が見つかるものです。
耐震性の不安があるなら、まずは調べて、知って、向き合うこと。
専門家に相談すれば、意外と現実的な手段が見つかるものです。
安心して暮らせる家があること。
それが、地方を支える何よりの力になるはずです。
それが、地方を支える何よりの力になるはずです。